まちの文化財(15) 中瀬金山の山臼

山臼

自然金
中瀬金山は、天正元年(1573)に、八木川の大日淵で砂金が発見されたことを契機となって鉱脈が発見されました。最初に発見された鉱脈は、石間歩とよばれる中瀬鉱山で最も大きな坑道です。
天正13年、天下を統一した秀吉は、中瀬金山を直轄地である藏入地としました。そして八木城主の別所重宗を代官に任命して治めさせました。
中瀬金山四百年フェスタが平成17年9月23日から25日まで3日間、関宮地域の中瀬区体育館で開催されました。
中瀬金山は日本精鉱株式会社が所有する鉱山です。金は、1トンあたり5グラムの含有量があれば採算がとれましたが、含有量が減少した結果、昭和44年に閉山しました。昭和10年から同44年までに生産された金は、7.2トンにも及びます。
中瀬の金光寺付近の畑では、今も江戸時代に金鉱石を砕くときに使った臼の破片を見ることができます。これは、金山でも特有にみられる金山の臼で、山臼と呼ばれます。
鉱石研究者の工藤知巳さん(朝来市在住)は「鉱石を300度の火で焼いてもろくして砕きます。そして鉱石を叩いて小さくします。それから山臼を使います。山臼の中心の穴に、水といっしょに鉱石の粒を入れて石臼をひきます。細かくなった泥水を比重選鉱して金を取り出します」と解説しました。
山臼は直径40センチメートル、厚さ20センチメートルほどの自然石で、中央に直径4センチメートルほどの穴があります。中瀬集落で見られる山臼は、江戸時代にも多くの金が採れた証拠を伝えています。
金の粒子の多くは10ミクロンほどで、肉眼では確認できない小さな粒です。しかし、中瀬金山の自然金には、長さ7センチメートルもある棒のような結晶もあります。日本最大の自然金だとも言います。
昭和32年、中瀬鉱山では400人を超える人々が働いていました。秀吉の時代から400年も続いた金山の繁栄を知るイベントとして、中瀬金山四百年フェスタを開催しました。
歴史文化財課
〒667-1105
養父市関宮613-6
電話番号:079-661-9042
ファックス番号:079-667-2277
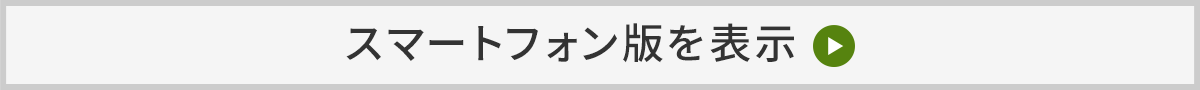







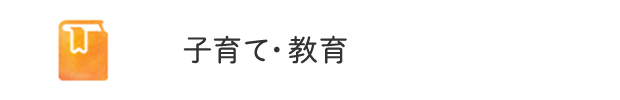




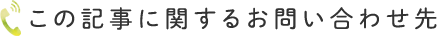
更新日:2019年11月14日